第24章 統合失調感情障害という難問v2.0
24-1 統合失調感情障害の5つのモデル
24-2 統合失調感情障害の現象学
24-3 遺伝
24-4 経過
24-5 治療反応
24-6 判定
—–◎ここがポイント◎——————————————
・統合失調感情障害の診断はしばしば厳密さに欠けている。
・注意深く評価すれば患者は3群に分類できる。
・第一群は精神病性よりも双極性が強いもの。たぶん、双極性障害の重症型変異で攻撃的な気分
安定薬治療が必要である。
・第二群は感情障害性よりも精神病性が強いもの。多分、統合失調症の軽症型変異。攻撃的な抗
精神病薬治療を要する。
・第三群は感情障害性と精神病性が同じ程度のもの。たぶん真実の感情障害と統合失調症の合併
。抗精神病薬と気分安定薬または抗うつ薬による攻撃的な治療が必要。
24-1 統合失調感情障害の5つのモデル
統合失調感情障害の理解の仕方として、5種類の理論にまとめられる(表24.1)。
—–表24.1 統合失調感情障害の5つのモデル—–
1.独立した病気。
2.精神病連続体の中間形態
3.統合失調症と感情障害の合併
4.双極性障害の重症型変異
5.統合失調症の軽症型変異
第一の考えは、統合失調感情障害は独自の病気であって、他の病気とは独立と考えるもの。
DSM-IVではご立派な独立した診断基準を立てていることから、からうっかりするとこれが正しい
考えのように見える。
第二は、まず双極性障害から統合失調症に至る精神病連続体があり、統合失調感情障害はその中
間的な臨床的状態像であると考えるもの。
つまり、このモデルではクレペリン大先生の、双極性障害と統合失調症の例の二分法を否定して
いる。
第三は、統合失調感情障害は感情障害と統合失調症の偶然の合併であると考える。したがって、
クレペリンの二分法は維持されている。症状のオーバーラップについては、両者が偶然合併した
ものと説明される。
第四は、統合失調感情障害は基本的に双極性障害の変異種であるとする。
第五は、統合失調感情障害は統合失調症の変異種であるとする。
24-2 統合失調感情障害の現象学
診断学は医師が最も関心を寄せる部分だが、診断学の観点からは、「統合失調感情」の用語は、
簡単に言うと精神病症状と気分症状の混合する症状をもつということだ。
気分障害と違うのは、精神病症状は短期間ではないこと。
統合失調症と違うのは、気分症状は不可欠であること。
臨床的には多くの患者がこのオーバーラップ領域に入る印象がある。
(統合失調症という円と気分障害という円が完全に離れていないで一部重なっているということに
なる。)
事実、こうした症状オーバーラップのある患者の発生を記述した原著論文が出版されたのが1933
年である。
クレペリン自身もかなり多くの患者で躁うつ病と早発性痴呆の症状のオーバーラップが見られる
と観察していた。
そうしたオーバーラップが起こることは当時から広く受け入れられていた。気分障害と精神病は
違うものだという考えの創始者であるクレペリンでさえ受け入れていたのである。
【この部分はやや追加の解説が必要である。シュナイダーのシゾフレニーの一級症状、二級症状
で考えると、うつ状態は明確に二級症状に分類されていて、診断的価値は一段劣るが、シゾフ
レニーを考える手がかりになるとされている。ここでは精神疾患の診断階層表が問題になるわ
けで、クレペリンとかシュナイダーでは、まず身体疾患、たとえば甲状機能亢進症などを除外
する。つぎにシゾフレニーを鑑別する。シゾフレニーが除外されたら躁うつ病を考え、それが除
外されたらうつ病を考え、さらに除外されたら当時で言う神経症を考え、さらには性格障害を考
える。てんかんや発達障害は完全に器質性のものであって、身体疾患除外の際にまとめて除外し
ているはずである。シゾフレニー、双極性障害、うつ病、当時の神経症、これらいずれも、いっ
たん大人として完成して問題なく機能していたというのが前提である。いったん正常機能を達成
していた個体が早発性痴呆になったりうつ病になったりするから、「病気」だろうと思うわけで
、正常機能を達成できていない場合には分類は別になる。
だからこの部分では、クレペリンがオーバーラップを認めていたというよりは、クレペリンは、
オーバーラップがある場合は、シゾフレニーの症状の一部だと整合的に理解てしていたと考えて
もいいと思う。
現在のDSM-IVでは、統合失調感情障害とするか、感情障害の中での分類として精神病性感情障害
とするかの問題になる。】
【第一章でクレペリンからブロイラーへ、そしてDSMへという流れを解説しているが、再論す
ると、まずクレペリンは、現在症からは診断しきれないと判断して経過を重視した。その結果が
、循環性の躁うつ病と慢性崩壊性の早発性痴呆だった。しかしそれでは目の前の患者をどう診断
して治療するのかという難問が発生し、やはり現在症・状態像診断をしようとブロイラーは考
えた。その際に、シゾフレニーの診断見落としが一番よくないことと考え、シゾフレニーの可能
性を最大限に考え、感情病はそれ以外、というような位置づけになった。現代のDSMでは現在症
重視は同じであるが、シゾフレニーにも気分障害にも均等程度に配慮していると思う。】
オーバーラップがあるということそれ自体は統合失調症と気分障害の診断カテゴリーを無効にす
ることはない。
このことの理由の一つとしては、症状論は4つの診断的妥当性検証要素のひとつに過ぎないからで
ある。 【4つの診断妥当性検証要素というのは表1.2のこと。症状だけではなく、経過、治療反応
、遺伝にも注意しようという話。】
—–表1.2 精神科診断妥当性検証セット—————–
1.症状
2.経過(初発年齢、自然経過)
3.治療に対する反応
4.遺伝歴
また別の理由としては、症状の違いは全か無かの現象ではないからである。
つまり、統合失調症と気分障害は症状が違うということは、2つの病気がオーバーラップしないと
いうことではない。
そして実際、かなり完成された症状の出現率を研究すると、気分症状と精神病症状を持つ患者は2
つの大きなグループに分けられる。1つは主に気分症状を呈し、1つは主に精神病症状を呈する。
当然ながら少数のオーバーラップはある(図24.1)。
統合失調気分障害の存在そのものが、統合失調症と双極性障害のクレペリンの二分法に対する反
例だとときどき議論されるが、前述の考察で明らかであるように、これは正しくない。
少数のオーバーラップは予想されることで、症状は診断的妥当性検証要素の一側面に過ぎない。
クレペリンの診断的図式を否定するためには、遺伝、経過、治療反応データを見る必要がある。
24-3 遺伝
—–キーポイント————————————
もし統合失調感情障害がそれ自体独立の病気であるとすれば、家族内で純種が育つはずである。
しかし、ほとんどすべての遺伝研究は、家系内での純粋培養はないことを示している。
統合失調感情障害は統合失調感情障害を持つ人の家族に主に見られるということはない。
むしろ、いろいろな研究がユニークなパターンを示唆している。
双極性障害の人の家族についての研究では統合失調感情障害双極タイプの発生頻度が高かった。
統合失調症の人の家族についての研究では、統合失調感情障害うつ病タイプの発生頻度が高か
った。
二つの疾患群を比較する完成された研究がいくつもあり、統合失調感情障害の人の家族を比較対
照群とした場合に、統合失調症または双極性障害の人の家族の方が、統合失調感情障害の発生頻
度は高かった。
こうした結果の解釈はいくつも可能である。
一部の人の場合には、統合失調感情障害双極タイプは双極性障害の重症型変異と考えられる。
また一部の人の場合には、統合失調感情障害うつ病タイプは統合失調症の軽症型変異と考えら
れる。
さらに一部の人の場合には、統合失調症と双極性障害の両方の家族において発生頻度が高いこと
から、二つの説明が可能である。
(1)統合失調感情障害は実は双極性障害と統合失調症を分けるクレペリンの二分法に対する反例で
ある。精神病は一体の連続のものである。
(2)統合失調感情障害は単に統合失調症と双極性障害(または単極性うつ病)が偶然合併したものに過
ぎない。
糖尿病と気管支喘息が同時に存在するようなもの。
そんなわけで、統合失調感情障害に関する遺伝学は、統合失調感情障害が独立疾患である可能性
を否定している。しかし表24.1に示した2から5の4つの可能性は残されている。
24-4 経過
—–キーポイント—————————————
統合失調感情障害の経過に関する研究ではおおむね一致が見られている。
経過は双極性障害よりは重症であり、統合失調症よりは軽症である。
さらに、統合失調感情障害うつ病タイプは統合失調感情障害双極タイプよりも回復が悪いように
見える。
これらの所見もまた残り4つのモデルと矛盾しない。
もし、ただひとつの精神病連続体というものがあるとしたら、双極性障害は軽症側、統合失調症
は重症側、統合失調感情障はその中間ということになる(図24.2)。この場合統合失調感情障害は双
極性障害と統合失調症の中間の経過をたどる。
他方、もし、合併症ならば、統合失調症の重篤な結果が、双極性障害の併存によって軽減されて
いて、統合失調感情障害では中間的な経過が見られる可能性がある。
さらに、もし、統合失調感情障害双極タイプが双極性障害の重症変異型であれば、双極性障害よ
りは悪く、統合失調症よりは良好な結果が予想される。
また、もし、統合失調感情障害単極性うつ病タイプが統合失調症の軽症変異型であれば、感情障
害因子に関しては統合失調症因子よりは治療に反応しやすいので、統合失調症よりもよい経過を
期待できる。
まとめると、経過研究は遺伝研究と同様で、独立疾患であるという仮説だけを否定し、あとの4つ
は依然として支持されている。
24-5 治療反応
治療反応は最も特異性の低い診断的チェック項目であるが、やはり有用である。
統合失調感情障害の治療についての研究は少ないのであるが、全般に抗精神病薬の長期治療を要
すると考えられており、その点では統合失調症と同じである。そして、気分安定薬(双極性タイプ)
または抗うつ薬(単極性うつ病タイプ)による長期治療が必要であり、それは対応する感情障害と同
じである。
また、この治療反応パターンは独立疾患モデルを否定し、他の4つのモデルを支持している。
24-6 判定
結論はどうか?
もっとも明らかなのは、DSM-IVで存在するかのように書かれているのに、実はエビデンスがな
くて、統合失調感情障害は統合失調症や双極性障害と分離される独立の疾患ではないことである
。
症状研究はさまざまであるが、重要でよく完成された研究による結論では、統合失調症と感情障
害は症状で鑑別できる。
症状の違いの研究は、おおむね、精神病を統合失調症と感情障害の二つに分けるクレペリンの二
分法に沿ったものである。
オーバーラップ領域があるとはいうものの、このようなオーバーラップはこの世界では、ヒトに
も動物にもその他の領域でもあることだと思う。
従って、現象学研究は単一精神病連続体モデルを否定する方向で解釈されていると言えるだろう
。
もし統合失調感情障害が統合失調症と双極性障害の合併したものだとすると、統合失調症と双極
性障害の発生率よりも、統合失調感情障害の発生率は非常に低いことが予想される。
つまり、統合失調感情障害は非常にまれであるはずであり、その理由は、合併症は偶然以上に頻
繁に起こるはずはないからである。
臨床的な印象とは反するのであるが、疫学的発生率研究では、統合失調感情障害は非常にまれで
あり、0.5%以下である。それは統合失調症(1%)、双極性障害(2-4%)という一般に受け入れられて
いる数字よりもずっと小さい。【0.01 0.02=0.0002 で0.02%だから、0.5%だと単なる偶然ではな
いと思うが?下記の3が0.02%にあたり、他の部分は1と2に相当するのだろう。】
このような考察から、表24.1のあげた1から5のなかで、1と2は否定されて3から5の3つが残る。
以上をまとめて最終モデルを提案したい。残った3つの理論を統合して、私の臨床経験を加えたも
のである(図24.3)。
1.双極性気分症状が主体で、精神病要素は少量のみという一群。診断は統合失調感情障害双極タ
イプ。双極性障害の重症型変異。たいてい、攻撃的気分安定薬が必要。さらに抗精神病薬を幾分
か攻撃的でなく使うかもしれない。予後は比較的良好。
2.精神病症状が主体で、単極性うつ病症状は少量のみという一群。統合失調感情障害うつ病タイプ
と診断される。統合失調症の軽症型変異である。たいてい、攻撃的抗精神病薬が必要。さらに抗
うつ薬を幾分か攻撃的でない程度に使うかもしれない。統合失調症よりも予後は良好だが、しか
し通常はわずかに良い程度。
この群が統合失調症と区別されるのは大うつ病エピソードが合併する点である。
大うつ病エピソードでは、1つまたは2つまたは少数のみのうつ病エピソードを経験し、それは短
期間で、エピソード同士の間が離れていて、しばしば心理社会的きっかけがある。
統合失調感情障害うつ病タイプでは、うつ病エピソードはより頻回で、より持続期間が長く、し
かし精神病症状よりも軽症であることがしばしばである。
3.真の統合失調感情タイプ。精神病症状と感情症状をほぼ等しい量で経験する。この群では真に統
合失調症と感情障害とが合併していて、中間的な経過をたどる。気分安定薬または抗うつ薬のど
ちらかと、抗精神病薬と、合計2つの薬剤を、攻撃的に持続的に長期間投与する。
統合失調感情障害の中での鑑別をしていくと、最終的にはこの3つの群になると思う。
この分類がベストだと思うが、こうして分類すると、治療がよく分かる。

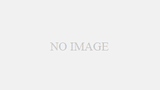
コメント